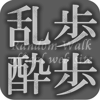―――明確な目的もなく、どこか矛盾していて、日常の中に隠されている非日常。それでいて純粋さの見失わない物語を創りたかった。
私は普段物語を考えるとき、読者に伝えたいことは明確に、しかし、押し付けがましくならない、説教臭くならない表現にするよう、心掛けてきた。伝えたいメッセージを分厚いオブラートに包むその心掛けは、非常にフラストレーションの溜まるものではあったが、読者の心象を優先する上では大切なことだと思っている。そこに生まれる不完全燃焼さは、次回作への欲求に置き換えてきた。
今回のプロジェクトを企画した段階で、作品内容に関する唯一の制約は「読者を意識しながら、読者に媚びないもの」であることだった。平たく言えば、「最後には人様に読んでもらうけど、まぁ自分が納得するものを好きに創れ」という感じである。そして、カミングアウトをすると、私が企画発案段階でこの制約を設けたのは、自分の作品に対する言い訳を作るためだった。つまり私は、先に述べた非常にフラストレーションの溜まる心掛けを、正当な理由をつけて取っ払いたかったのである。オチがなくても良いじゃない!説教臭くても良いじゃない!押し付けがましくて何が悪いの!描きたいものを描くんじゃー!…という感じである。閑話休題。まぁおかげ様でと言っては何だが、説教臭くて自己満足度の高い、一人よがりで、それでも納得のいく作品ができたと思っている。
ここで一つ主張をしておくが、この物語はラブストーリーだ。誰かが「こんなのラブストーリーじゃねぇ」と言っても、これは間違いなく「愛の物語」である。胸をキュンとさせるエピソードも、ドキドキさせる展開もないが、こんな内容のラブストーリーがあってもいいではないか、と言っておく。
音無綴には、意図的にモノローグをつけなかった。何を考えているのか、何故この行動をとったのか、結局、こいつは何がしたかったのか―――その全てに明確な答えを出さないまま、どこか違和感のある、曖昧な印象の人物として物語を終えたかった。正直に話すと、「性の選択ができる」というファンタジーとしては使い勝手の良い設定も、結局は音無綴を、男でも女でもない曖昧な存在にするための後付けに過ぎない。(参考までに言っておくと、イベントの出張編集部に持ち込みをした際、多分編集さんはこの設定を膨らませて物語が進行していくと思っていただろうし、まぁ商業誌的にはそっちが正解だと思う。)
何とも使い勝手の悪い主人公をよそに、他の二人はそれなりに良い働きをしてくれた。高垣呉羽は、この物語の良心としてアクセントになってくれたし、その実直さで多数派の人が持っているであろう価値観を体現してくれた。そして神久呂悠は、その説教臭さと、ほのかに香るウザさを最大限活かし、物語をおし進めてくれた。特に彼は、綴の気持ちもある程度察し、呉羽の感情も理解していたので、場面ごとの繋ぎの役割を果たしながら、この物語の押し付けがましい部分を一身に担ってくれた。ある意味この作品は、彼の物語と言っても良いかもしれない。
愛する、という想いには多種多様、本当に様々な形がある。多数派である異性愛の他にも、同性愛、両性愛、非性愛、無性愛、もちろん親愛や友愛、そしてこれらにも含まれない愛の形だって、沢山あるだろう。この物語での音無綴の役割はまさに、その名前もない愛の形の体現化にあった。歪で、一人よがりで、幼稚で、でもどこか達観していて、形が掴めず、それでも一概に否定はできない愛の形を、その中に残る純粋さと共に表現したかった。
偶然にも、今回のプロジェクトで制作された作品はすべて、「愛」がテーマとなっている。そして見事に全作品、方向も形もアプローチの仕方もまったく異なっていた。同じテーマを見据えながら、ここまで違うジャンルのものができるのかという発見や、逆に、複数人から同一のテーマが出された面白さ、作業工程の違いなども、やはり単独作業では知ることのできなかったものだろう。それ以外の様々な場面を見ても、このプロジェクトは「次」に繋がるものになったと思っている。
愛という言葉を連呼しすぎてやや気恥ずかしいが、最後に…この物語を読んで、マイナスでもプラスでも何らかしらの感情を抱いてくれる人がいれば、ぶっちゃけもう万々歳だ。もちろん、あとがきで語っている偉そうな内容が、そのまま、作品の方で上手く表現できているとは思っていない。様々な面が未熟であり、不格好なものだろう。それでも、今自分ができる精一杯の愛情を込めて、この物語があなたの心まで届くように、そして贅沢をいうなら、あなたの心の琴線に触れるものであればと、願っている。
あとがき
あとがき
あとがき
あとがき
秋勇